※本記事にはPRリンクが含まれています
職場でのリーダーとは何か?
なぜ部下とは距離を取らなくてはいけないのか?
マネジメントの方法がわからない——。
中間管理職なら、このような悩みを一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
管理人について
私は17年目の理学療法士で、毎日読書や運動を5年以上継続しています。
40代からの成長について日々発信しています。
この記事では、中間管理職のマネジメントについて、安藤広大氏の『リーダーの仮面』を読んで気になった点をまとめています。
この記事でわかること
- 部下との適切な距離感
- 成長する組織の思考法
- ルール設定の必要性
結論を先に伝えると、リーダーという仮面をつけて、職場ではマネジメントに徹するということです。
気になる方はぜひご覧ください。
この本を読もうと思った背景
私が『リーダーの仮面』を手に取ったのは、自分自身が中間管理職で主任という立場にあるからです。
正直なところ、マネジメントについて体系的に指導されたことはなく、これまで自分なりに考えながらやってきました。しかし、実際に本を通じてマネジメントについて学ぶことも必要だと感じ、中間管理職向けに書かれた本書を読むことにしました。
今の自分に足りないものは何か。それを知りたいという思いが、この本を開くきっかけになりました。
本の概要
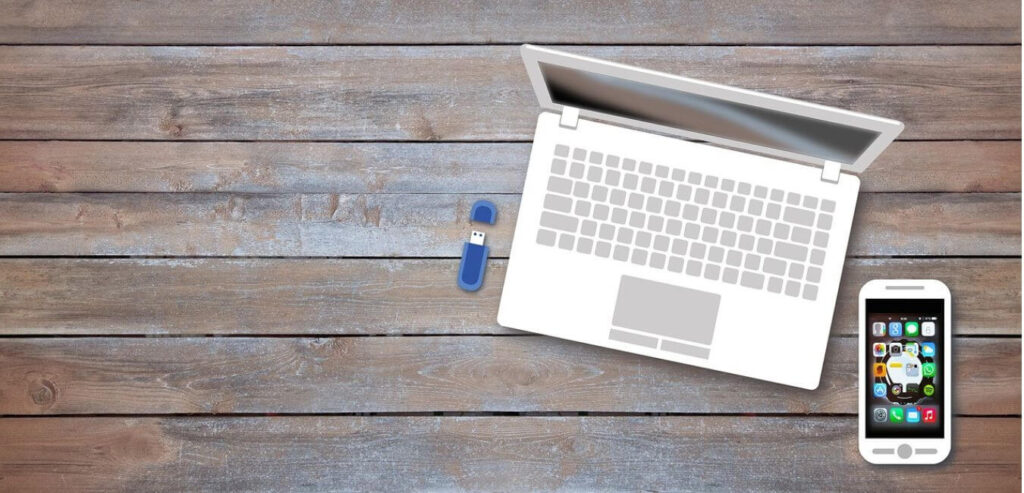
著者について
著者:安藤広大
株式会社識学 代表取締役社長
1979年大阪生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社NTTドコモを経て、ジェイコムホールディングス株式会社の取締役営業副本部長等を歴任。2013年、「識学」という考え方に出会い独立。2015年、識学を一日でも早く社会に広めるために株式会社識学を設立。
代表的な著書に『伸びる会社はこれをやらない!』などがあります。
本書の構成
- はじめに: なぜリーダーの言動が大事なのか?
- 序章: リーダーの仮面をかぶるための準備
- 第1章: 安心して信号を渡らせよ
- 第2章: 部下とは迷わず距離をとれ
- 第3章: 大きなマンモスを狩りに行かせるな
- 第4章: 褒められて伸びるタイプを生み出すな
- 第5章: 先頭の鳥が群れを引っ張っていく
- 終章: リーダーの素顔
個人的には、マネジメントで部下と距離を取る点が気になったのと、成長していく組織にしていくにはどうすればいいのか、という点に焦点を絞って読んでいきました。
正直に言うと、自分とはあまり考えが合わない部分もありました。わからなくもないけど、理解しにくい——そんな印象です。
でも、本気でマネジメントするとはこういうことなのだろうなと、なんとなく感じた一冊でした。気になる方はぜひ本書を手に取ってみてください。
心に刺さった3つのポイント
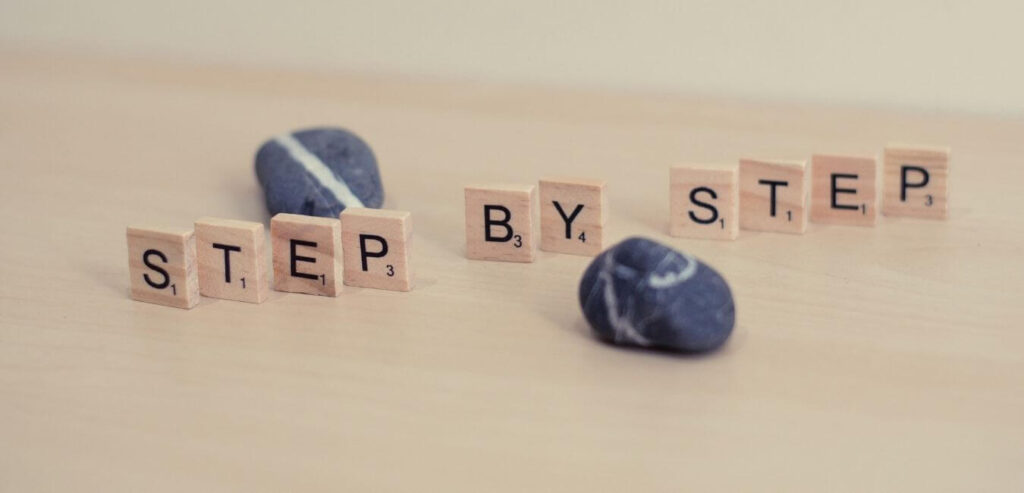
私が本書を読んで頭に残っているのは、次の3点です。
- ルールをしっかり決めて守らせる
- 部下とは距離を取る
- 成長できる組織にする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ルールをしっかり決めて守らせる
本書では、ルールを「姿勢のルール」と「行動のルール」の2つに分けています。
姿勢のルールは、挨拶などのことです。やろうと思えば誰にでもできる——それが特徴です。やるかやらないかは、その人次第。
行動のルールは、「今日は営業で3件回る」といった、具体的に数字で表せるルールです。
このようなルールを徹底することで管理していくことが、マネジメントの基本だと本書は説きます。
これは私も強く納得している点です。ルールが曖昧だと、仕事をやる職員もいれば、やらない職員もいる。そうなると不公平感が生じ、不平不満の原因になることが多いんですよね。
ルールをしっかり守る——個人的にはこの考え方に賛成です。ルールを決めると窮屈だと感じる人もいるかもしれませんが、むしろルールがない中で曖昧さや不公平が生じる方が、職員にとってはストレスになります。そのストレスをいかに軽減してあげるか。それが、このマネジメントの良いところだと感じました。
部下とは距離を取る
2つ目に気になったのは、部下と距離を取るということ。
確かに職場は仕事をする場所なので、部下と友達になったり、馴れ合う関係というのは良くないと私も思っています。ただ、部下とどの程度距離を取るのかというのは、常日頃から難しい課題だと感じています。
本書での「部下との距離を取る」というのは、事実ベースで指導すること、そして決して感情的な指導にならないというところがポイントだと感じました。
距離を取る上で大事なのは、やはりすべての部下に対して公平さを保つということ。「この部下とは仲が良いけど、この部下とはあまり仲良くないから話さない」といったことがないようにする——それが重要だと感じました。
わざわざ冷たい人間を演じる必要は個人的にはないと思っていて、あくまでも一定の距離を保ちつつ、良好な関係を築くことが必要なのではないか、と考えています。
成長できる組織にする
成長できる組織を作るのは、確かに大変です。他人が自ら勉強して学び、成長するように工夫するのは難しい。そもそも私は、他者を変えることは難しいと思っています。
本書では、職場内で競争させることが重要だと述べています。競争させることで闘争心を煽り、自ら勉強したり業績を上げようと必死になる——そういうことなのかもしれません。
ただ、私のリハビリの現場であれば、たくさん患者さんをリハビリした人が評価されるような仕組みになってしまいます。すべての業種に当てはまるマネジメント手法ではないな、と感じました。
成長というのは、競争させれば芽生えるというものでもないかな、と個人的には思っています。成長する組織を作るというのは難しい。ここは今後も悩み続けるところだと感じています。
以上が、本書を読んでの一番の気づきです。
読んでよかった?行動や思考はどう変わったか
本書を読んで変わった点は、とにかくルールをしっかり守らせることの重要性を再認識したことと、部下との接し方には公平性が必要だと改めて感じたことです。
当院ではルールが曖昧であったり、部下との公平性が保たれていないことが、職員間の分断を生んでいるような気がします。今後はその点を改めて、少しずつ改善していこうと考えています。
自分の中で「これはやるべきだ」という確信が持てたことが、この本を読んだ最大の収穫でした。
こんな人におすすめ
本書がおすすめなのは、次のような方です。
おすすめ
- 中間管理職になったばかりの人
- マネジメントについて学びたい人
- 数字を上げなければいけない組織に勤務している人
これらの方には、参考になる内容が多いと思います。
私個人は、正直なところ考え方が違いすぎて理解に苦しむ場面もありました。しかし、全く考えが違う人の本を読むことも、視野を広げる上では重要です。良い経験になったと感じています。
まとめ
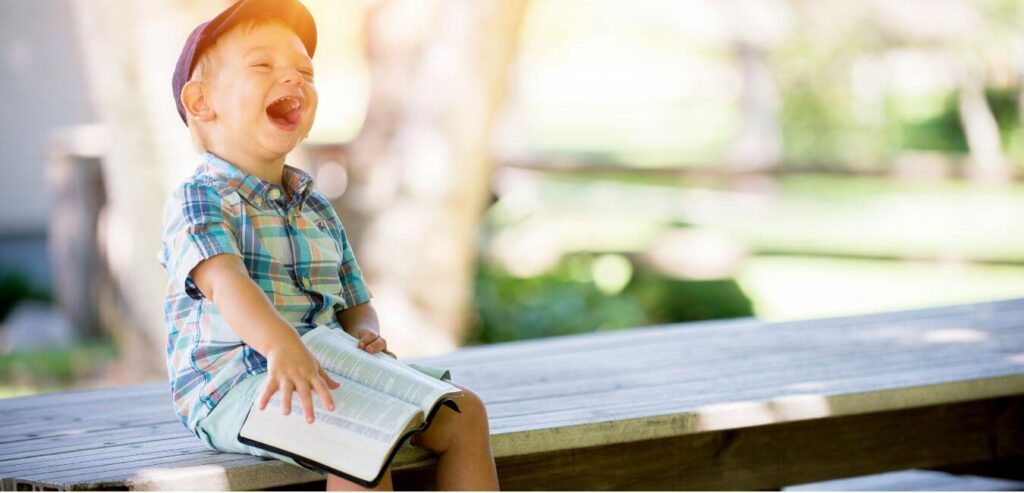
いかがでしたか?今回は『リーダーの仮面』についての書評でした。
個人的には少々理解が難しい内容も多かったのですが、人の上に立つのは厳しくもあり、やや孤独感も伴う仕事なのかもしれないと感じました。
リーダーとして重要になるのは、ルールがしっかり整備されていること。そして挨拶などの、誰でもやろうと思えばできるルールも設けなければ、職場全体の雰囲気も改善されません。それが大事だと感じました。
人をしっかり管理して、人の上に立ちたいという思いが強い方には、本書はとても参考になると思います。ぜひ手に取ってみてください。
