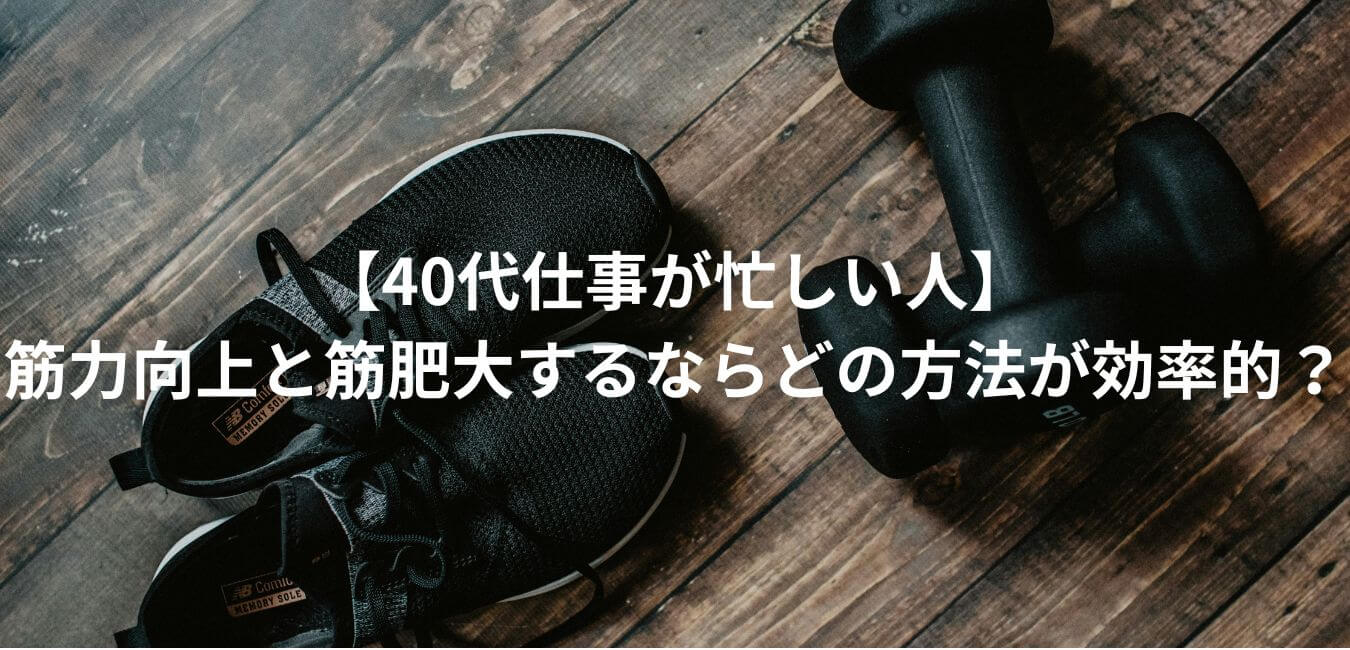※本記事はPRリンクが含まれています
- 筋トレしたいけど何から始めたら良いかわからない
- どのくらいやると筋肥大や筋力がつくの?
- 科学的に正しい方法が知りたい
働いている人世代なら効率的に筋トレに励みたいですよね。
管理人ついて
私は17年目の理学療法士で、糖尿病療養指導士の資格も保持しています。
運動・朝活・読書を5年以上継続しています。
本や論文で得た知識を生活に活かし、自分の体の変化について発信しています。
この記事では、筋力と筋肥大の効率的な方法を解説した論文を紹介しています。
この記事を読むことで、
- 筋力アップの方法がわかる
- 筋肥大の方法がわかる
- 科学的に正しい方法の知識が手に入る。
はじめに結論を伝えると、筋力向上には高負荷を用いた週3回のマルチセットが推奨され、筋肥大に対しては高負荷・マルチセットの週2回トレーニングが最も効果が高いです。
気になる方は是非読み進めてください。
テーマ提示:論文タイトル & 出典
今回、参考にした論文は以下です。
タイトル:「Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: a systematic review and Bayesian network meta-analysis 」 (健康な成人の筋力と筋肥大のためのレジスタンストレーニング処方:系統的レビューとベイジアンネットワークメタアナリシス)
著者と年代:ブラッド・S・カリアー(マクマスター大学)2023年
雑誌名:British Journal of Sports Medicine(英国スポーツ医学ジャーナル)
結論と結果を要約
記事の最初にも書きましたが、高負荷を用いた週3回のマルチセットが推奨され、筋肥大に対しては高負荷・マルチセットの週2回トレーニングが最も効果が高いという結論になっています。
つまり、筋力をつけたいなら、とにかく高負荷で複数セット数の筋トレを週3回。
筋肥大は高負荷で複数セット数の筋トレを週2回ということです。
この研究では全身法なので週2~3回です。 鍛える部位を分ける分割法だと頻度は毎日になりそうですよね。
その場合は、鍛える部位が胸の日は月・木。
足の日は火・金などに分けるということです。
個人的には、筋肥大して身体を太くしたいのと、引き締まった身体にしたいので、筋肥大トレーニンを意識したいと思いました。
自分の体験や臨床での気づき・自分の視点
今回この論文を読んで気づいたのは、
- 高負荷トレーニングが大事
- 部位ごとに週2回の頻度
- 同じ部位を3セットは行う
以上の3点を取り入れようと思っています。
わたしは、胸の日、腕の日、足の日で分けていますが、もう少しトレーニングメニューの組み合わせを考えたほうが良いかもと反省です。
各部位が週2回程度になるようにメニューと組み合わせを見直していきます。
ちなみに高負荷筋トレが自宅でも出来るように、40kgまで重量を変えられる可変式ダンベル買いました。
まだまだ40kgには届きませんが、少しでも重量を増やしていけるよう継続するのみです。
臨床での活かし方は?
今回は健常者を対象にしているので、わたしが担当する患者さんや利用者さんには対象外になります。
担当患者さんがほとんどが80歳以上の高齢者なので。
ですが、筋力を上げるためには高負荷のトレーニングが効果がありそうなので、筋トレの負荷を可能な範囲であげてみても良いかもしれません。
あくまでもリスク管理しながらですが、盲目的に同じ内容で同じ回数はいけませんね。
読者への行動提案
今回の論文は、運動しない人よりも、筋トレした人の方が筋力も筋肥大もするという結果です。
また、
- 筋力向上には高負荷、複数セット、週3回
- 筋肥大には高負荷、複数セット、週2回
という結論でした。
筋肥大の頻度が1回少ないことを考えると、筋肥大には少し休息も取ることが大事なんだと推察されます。
上記の結論は筋トレでは当たり前だし、トレーニーの方なら誰もが知っている事実だったかと思います。
しかし、何千人を対象にして、何百という研究結果をまとめてくれた研究はとても貴重だし勉強になりますよね。
また科学的なエビデンスレベルも高いので信頼できます。
自分のやってきたトレーニングは間違いではなかったと再確認する機会にもなります。
最近は動画でも筋トレを解説してくれているチャンネルは多いです。
わざわざ論文を読まなくても筋トレについて学べますが、間違った方法も発信されていることが少なくありません。
だからこそ、実際に科学論文を読み、自分の目で事実を確認することもこの時代には必要なことだと感じます。