「思い込みが激しい」「自分の考えは正しい、相手が間違っているんだ」——人間はこのような考えに支配されやすいと感じませんか?
正直に告白すると、私自身も自分の考えが正しいと思い込んでいるため、再度考え直したり、相手の意見を取り入れようとはなかなか思えません。
すでに正しいと思い込んだことを考え直すのは、本当に容易ではないのです。
本書『THINK AGAIN』は、「再考」について書かれた一冊です。
著者アダム・グラントの目的は、既存の考え方を新しい観点から見つめ直すことがいかに大切かを伝えること。
自分の考えは間違っていないと思い込んでしまうのは誰にでもあることだからこそ、ぜひ本書を手に取ってほしいと思います。
この本を読もうと思った背景
私が『THINK AGAIN』を読もうと思った理由は、次のようなものでした。
- 誰にでも思い込みはある
- 自分の考えを再考するのが難しかった
- 柔軟な思考力が欲しい
正直なところ、職場では上司と考えが合わず、居づらさや働きづらさを感じています。
お互いに自分の考えを譲らないところがあるのでしょう。
でも、私が柔軟な思考ができるようになれば、少しは生きやすい職場になるのではないか——そう思ったのがきっかけでした。
本の概要
著者について
著者のアダム・グラントは、ペンシルベニア大学ウォートン校教授で組織心理学者。
同大学史上最年少で終身教授に就任した人物です。
ベストセラーには『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代』や『ORIGINALS 誰もが「人と違うこと」ができる時代』などがあります。
本書の構成
本書は以下のような章立てになっています。
- プロローグ:思い込みを手放し、発想を変えるための「知的柔軟性」について再考する
- PART1:自分の考えを再考する方法
- PART2:相手に再考を促す方法
- PART3:学び、再考し続ける社会・組織を創造する方法
- PART4:結論
個人的には、自分の考えを再考することが何より大事だと感じています。
相手に再考を促す方法も書かれていますが、まずは自分が変わるところから始めるべきでしょう。
心に刺さったポイント
本書を読んで、特に頭に残っているのは次の3点です。
- 科学者の思考モード
- 無知を自覚する
- 謙虚でいる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
科学者の思考モード
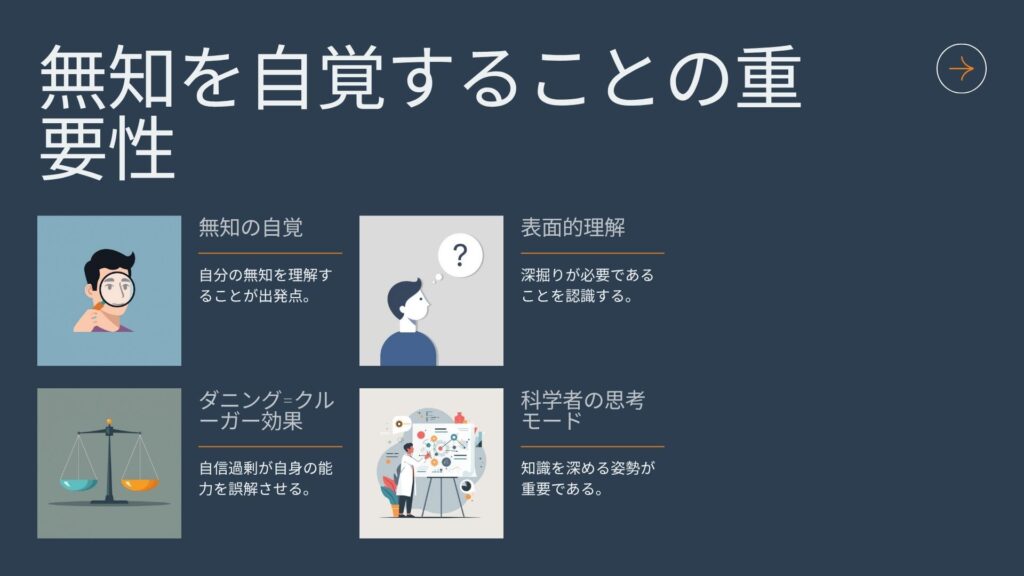
結論から言うと、科学者のように仮説を立てて物事を検証し、真実を追求するような考え方をするということです。
最近はSNSなどであまりにも情報が多く、その情報を何の疑いもなく真実だと受け入れてしまう人も多いですよね。
また、私の職場でのあるあるですが、人の噂をあたかも真実であるかのように受け取り、鵜呑みにしている人の多さに驚きます。
まずはこういったことを鵜呑みにせず、自分で考えたり調べたりすることが大事だと思います。
本書では、科学者の思考モード以外に3つの思考モードが紹介されています。
- 牧師の思考モード:自分の意見が正しいことを説く
- 検察官の思考モード:論理的に相手を批判する
- 政治家の思考モード:自分が正しいと周りに伝えて回る
確かに私にもこの思考モードは存在します。
自分の意見が正しいことを伝え、相手を論破し、根回しのように自分の意見と同じ人と固まる——。
このサイクルにハマると、自分の考えが正しいという思いが強まり、揺るぎないものになってしまいます。
誰からの意見も受け入れないし、考え直すこともない。
そしてこの思考モードは、誰にでも陥りやすい特徴があると感じます。自分を客観視できないと気づけないでしょう。
そこで科学者の思考モードが登場するのです。
科学者はまず自分の思考や考えを疑います。
本当に正しいのか? 相手のほうが正しいのでは? もしくはお互いが正しいのかも——。
仮説を立てて、さらに自分で調べ直す。そして自分で新たな結論を導き出す。
この科学者の思考モードができることが、思考の柔軟性を生むと考えます。
私も昔はすぐにSNSの情報を信じたり、噂話を信じたりしていました。
でも今は自分で調べる癖をつけ、信頼できる情報として論文や本を中心に、自分の考えを改めています。
無知を自覚する
科学者の思考モードでいるためには、自分がいかに無知であるかを知る必要があります。
すべてに詳しい人なんていませんよね。
でも人間は何でも知ったような気になってしまう。物事の表面しか分かっていないのに、すべてを知ったような気になってしまうのです。
ダニング=クルーガー効果といって、できない人ほど自分のことを過大評価することが分かっています。
つまり、「自分はみんなよりも優れている!」という思い違いをしているということ。恐らく私にも当てはまるような心当たりがあります。
私が思ったのは、物事をいかに深く知っているか、ということです。
表面的な知識は誰にでもそれなりにあるはず。でもさらに深掘りすることができるか——。
自分はまだまだ何も知らない。そう思うことが大事なのです。
そして、知らない新しいテーマを見つけては深く追求していくことが大切なんだと感じます。
謙虚でいる
最後に謙虚でいることについて。謙虚でなければ、無知を自覚することはできません。
自分の知識不足や過ちを素直に認め、謙虚でいる姿勢。これがあってはじめて無知を自覚することができるのです。
だから、今回の本書の学びは次のようにつながります。
- 謙虚でいることで
- 無知を自覚し
- 科学者モードになれる
謙虚でいることは、再考するためのスタートラインに立つこと。
人格や知識、アイデンティティを否定されると、人はイラッとしますし、感情的になりますよね。
そんなときでも謙虚でさえいれば、感情的にならず意見を聞いたり、相手の考えを冷静に受け止めたりすることができます。
そして自分の考えを再考し、間違いを認めることもできる。謙虚さも再考のスキルの1つだと学びました。
以上が、本書を読んでの一番の気づきです。
読んで変わったこと
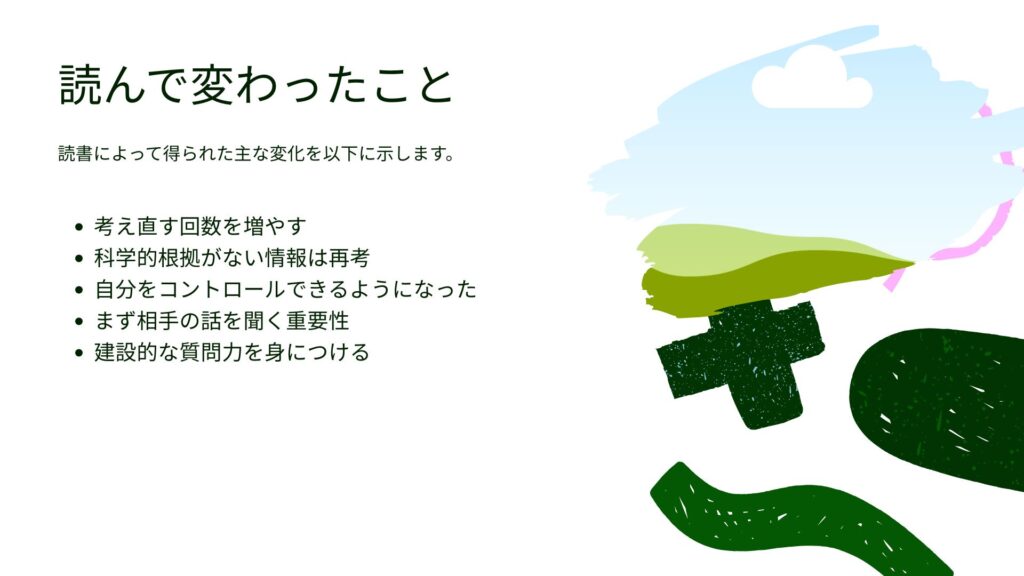
本書を読んで変わった点は、「考え直す回数を増やす」ということです。
論文などを読み、科学的に正しいと証明された内容であれば信じますが、そうでない場合は再考することが必要だと感じました。
また、読書や論文で得た知識があるからこそ、他者の意見を正論で正したくなる衝動に駆られます。
つまり検察官モードになりがちだからこそ、自分で自分を抑えコントロールすることもできるようになりました。
知識を得るにつれて、自分が正しいという思考になりがち——。
だからこそ謙虚になり、まずは相手の話を聞く。そして建設的な話ができるように、自分も質問する力を身につける必要があると感じました。これは今後の課題です。
こんな人におすすめ
本書がおすすめなのは、次のような人です。
- 自分は知識があると思う人
- 自分は頭がいいと思う人
- 相手を論破したい人
以上の人には特におすすめします。
自分をしっかり見つめ直すきっかけになるでしょう。そしてさらに、自分を成長に導いてくれるはずです。
まとめ
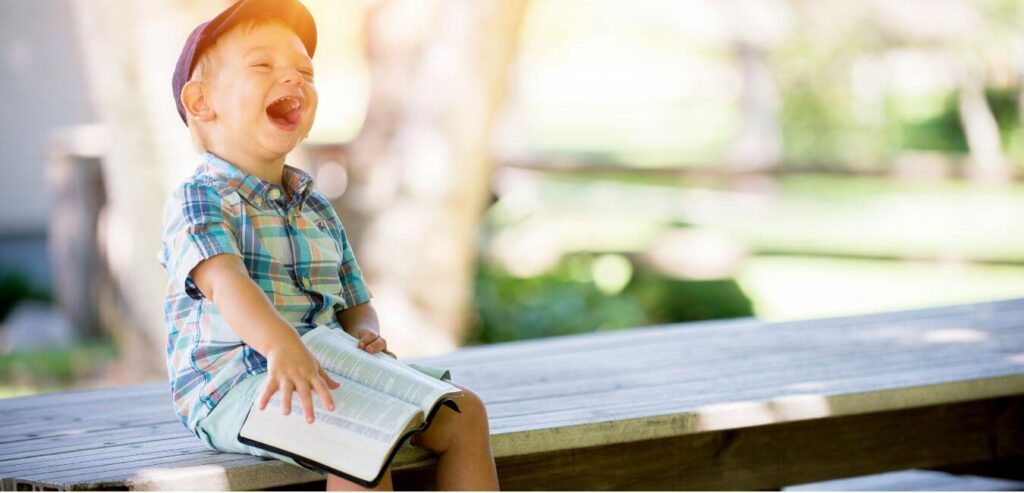
いかがでしたか?
今回はアダム・グラントの『THINK AGAIN』について書いてみました。
人は意識的に再考しようと考えることは少ないものです。
「これは正しいのか?」「なぜ?」「どのように?」
様々な角度から物事を見ていく「再考」は、今の世の中では必要な能力だと感じます。
SNSなどの情報に流されず、自分の頭で考え直す。
私も再考の癖をしっかりつけられるように、習慣に取り入れたいと思います。
皆さんも、ぜひ『THINK AGAIN』を手に取って、考え直す力を身につけてみてはいかがでしょうか。
